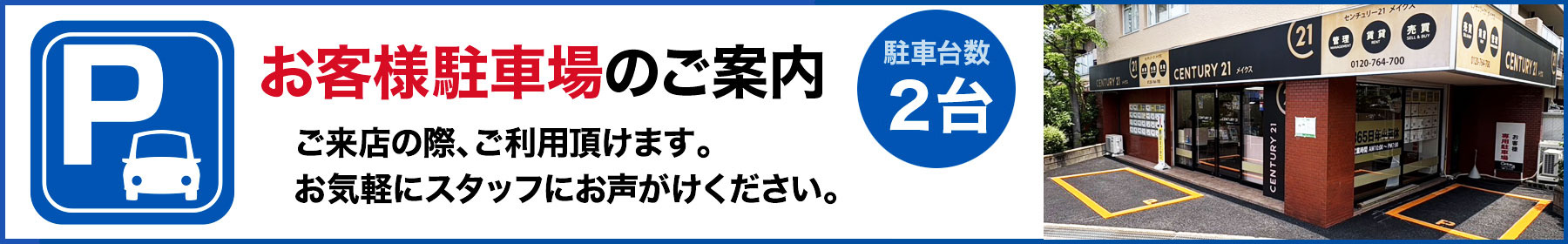巨椋池という名前は現在京滋バイパスの巨椋インターと第二京阪道路の巨椋池インターくらいしか見かけませんが、今から70年ほど前まで京都市伏見区の南部から宇治市の西部、久御山町の北東部にかけて、東西約4km、南北3km、周囲16km、面積約800ha(甲子園球場の約200倍)もの巨大な池がありました。
この池には北から桂川、南から木津川、そして東から琵琶湖から発する宇治川の3本の河川が合流し、淀川となって大阪湾へ注いでいました。
増水時には膨大な量の水が流れ込み、沿岸の低地ではわずかな雨でも水位が上昇し農地はすぐ浸水したため、むしろ漁業で生計を立てる人々の方が多かったようです。
そんな洪水を繰り返していた巨椋池ですが、安土桃山時代の1594年、豊臣秀吉によって伏見城の築城が始まって以降大きな変貌がありました。
その当時京都と大阪は淀川を利用し大型船も入ることが出来たので、軍事的にも物流的にも安定した船の運行と伏見の町を洪水から守るため、幾筋もの河道に別れて巨椋池へと流入していた宇治川を巨椋池と切り離す大事業が行われました。
その結果、宇治川は槙島堤によって北へ迂回する形となり、巨椋池とのつながりは淀付近のみとなりました。さらに伏見城下の南には現在の観月橋が渡され、太閤堤の上には京都と奈良を結ぶ大和街道が造られました。
しかし、伏見が港としての繁栄を極める中、淀付近で3河川と繋がっていた巨椋池は江戸時代に入っても水害が多発し頻繁に甚大な被害があったので、江戸時代初期に今度は木津川の付け替え工事をはじめ様々な治水対策がなされましたが相変わらず水害は続きました。
そもそも淀川の増水時に大阪平野を守るために、巨椋池に洪水調節のための遊水池としての機能を持たせるために、わざわざ淀付近で3河川との繋がりを残したとされています。
明治に入ってからも巨椋池周辺は水害が続き、下流の淀川でも大規模洪水が頻発しました。
又、大阪と伏見の間に大型の蒸気船が就航するようになり淀川の改修は緊急の課題となりました。その後改修工事は続きますがやはり洪水は無くなりません。そして明治38年、琵琶湖に南郷洗堰(なんごうあらいぜき)が完成します。
琵琶湖から流出する瀬田川の川幅を広げ、そこに巨大な堰を設置することで琵琶湖の水位を安定させ、宇治川の流量を調節するという画期的なものでした。この事業により長年巨椋池が果たしていた遊水池としての役割は必要なくなり、3河川の合流部分は付け替えられ現在の八幡市付近になりました。
②につづく
参照・引用 (一社)農業農村整備情報総合センター
京都府山城広域振興局
関連記事
- お知らせ 2018年5月17日 ローンがおりなかった場合、売買契約はどうなりますか?
- お知らせ 2025年10月2日 半白パーキング
- お知らせ 2025年4月7日 井川遊歩道〜桜〜
- お知らせ 2018年5月17日 再建築不可の物件とは?
- お知らせ 2018年5月17日 査定価格の仕組みを知りたい
- お知らせ 2018年5月17日 不動産の売却査定を依頼する際に準備しておくものは?