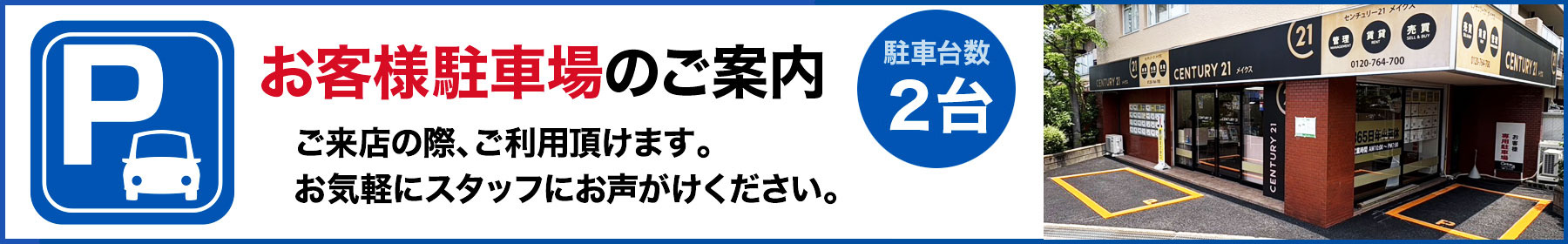近年、不動産(土地・建物)をお持ちの方が亡くなっても、相続登記がされないケースが数多く存在しています。
相談を受け所有者が誰なのかを確認するために、登記簿謄本を取得するのですが、相続登記がまだされていないということがあります。
相続登記がされないと、登記簿を見ただけでは、その不動産を誰が相続して、誰が所有者なのかがわからない、連絡をとりたくても相続人の住所がわからないので、連絡がとれない、 取引が円滑に進まないといった仕事面の悩みだけでなく、公共事業や、災害時の復旧復興が進まない、長年放置されていることで、隣地の人が清掃、苦情の連絡を取りたくてもとれず、 周囲にも迷惑がかかるということが起こっています。
このような問題は「所有者不明土地問題」といわれ、社会問題化しています。 (全国のうち所有者不明土地が占める割合は九州本島の大きさに匹敵するともいわれています。今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、 ますます深刻化するおそれがあり、その解決は喫緊の課題とされています)
このような所有者不明土地問題を解決するため、令和3年4月、「民法等の一部を改正する法律」が成立・公布され、令和6年4月1日から、 これまで任意であった相続登記の申請が義務化されることになりました。
相続が発生してもそれに伴って相続登記がされない原因として、
① これまで相続登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと
② 相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には、費用や手間を掛けてまで登記の申請をする意欲がわきにくい ことが指摘されています。
そのため、相続登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防しようというのが義務化の趣旨です。
相続登記の申請義務についてのルール
① 基本的なルール
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内
② 遺産分割が成立した時の追加的なルール
産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以
内 その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。
Ⓐ・Ⓑともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
※「被相続人の死亡を知った日」からではありません。起算点は不動産の取得時からです。
また今回の義務化に合わせて以下の制度も行われる予定です。
A 相続人申告登記
不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、 全ての相続人が法律で決められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態になります。
この共有状態を反映した相続登記を申請しようとする場合、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定しなければならないため、 全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本など)の収集が必要となります。
そこで、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みが新たに設けられました。
① 登記簿上の所有者について相続が開始したこと
②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができます。
この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分の割合までは登記されないので全ての相続人を把握するための資料は必要ありません (自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すればOKです)
B 所有不動産記録証明制度
登記官において、特定の被相続人(亡くなった親など)が登記簿上の所有者として 記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が新たに設けられる予定です。
また今回の相続登記の義務化に合わせて、所有者の住所等の変更登記も義務化される予定です。(令和8年4月までに施行予定) 登記簿上の所有者の氏名や住所が変更されてもその登記がされない原因として、
①これまで住所等の変更登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても所有者自身が不利益を被ることが少なかったこと
②転居等の度にその所有不動産について住所等の変更登記をするのは負担であること が指摘されています。
そこで、住所等の変更登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防しようとしています。 登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記 の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります
今回は所有者不明土地問題の解決のために、その他の不動産に関するルールが今後変更される予定です。
当社メイクスでは、提携している司法書士への登記相談だけでなく、相続される不動産の有効利用など無料相談でお受けいたします。 どのような対策が今ならできるのかアドバイスと手続きのサポートをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
その他詳細は以下リンクもご確認ください。
https://www.moj.go.jp/content/001375975.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001372210.pdf
関連記事
- お知らせ 2019年5月17日 宇治市でのびのび子育てしてみませんか④ 三室戸寺
- お知らせ 2018年5月17日 家賃の支払いについて自分で決めてもいいのですか
- お知らせ 2018年10月17日 宇治市でのびのび子育てしてみませんか
- お知らせ 2019年8月17日 京阪宇治線について
- お知らせ 2024年12月30日 年末年始のご挨拶
- お知らせ 2018年5月17日 土地を購入する際に必要な準備について