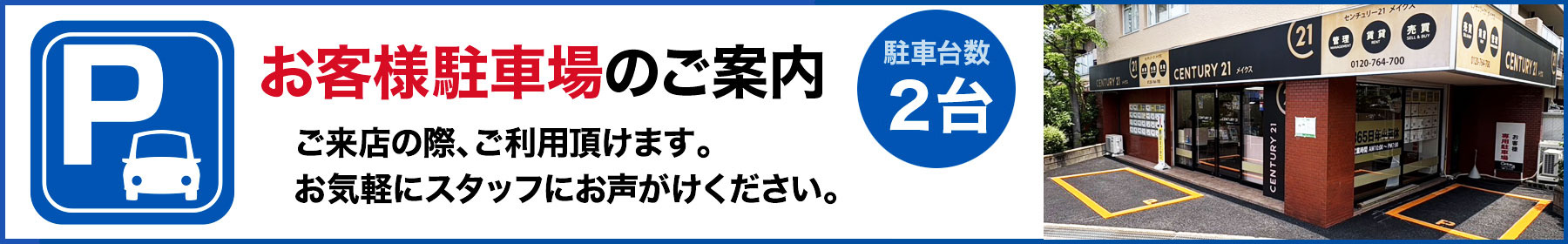宇治市の地形、災害、ハザードマップについて
①宇治市の地形
宇治市域は東部の醍醐山地、中部の山麓丘陵地、西部の沖積低地の3つに区分されます。市のほぼ中央には南北に宇治川が流れ、沖積低地と山麓丘陵地に広がる市街地を二分しています。
(1)標高約350~600m級の山頂が連なる醍醐山地は、笠取川や志津川が谷を 形成し、川沿いに山間農地が発達し、田畑や杉林といった山里の風景が広がっています。更に宇治川の本流が醍醐山地の南縁を東西に横切り、深い峡谷地形を形成しています。
(2)中部の山麓丘陵地帯には構造地形や段丘地形がみられ、1960年代以降の人口増加に伴って開発された住宅地が標高約 50~80mほどの一帯に広がっています。
(3)西部の沖積低地は標高 50m以下の低地で、田畑や住宅地、自衛隊施設や学校などの施設があります。更にこれらの西側には巨椋池を干拓した低湿地帯があり、農地と住宅地が広がっています。
主要河川としては、宇治川が流れています。琵琶湖を水源として流出する唯一の川で,京都・大阪の府境付近で桂川,木津川と合流して淀川と名を変えるまでの流路の長さは約30kmあります。上流は瀬田川といい,宇治市に入って宇治川と名を改めます。滋賀県全域の流水はすべてこの川に流れこむために流量は大きく,巨椋池(おぐらいけ)干拓地周辺が水害を受けることが多く,1953年9月の台風13号による水害を契機に宇治川の治水事業が進展しました。
その他宇治市の地形の歴史は、https://www.city.uji.kyoto.jp/…/7147/31syou(280330).pdf
をご参照下さい。
②災害、ハザードマップ
平成24年8月13日、14日に宇治市北東部の弥弥次郎川の堤防が決壊し、複数の中小河川で氾濫、溢水が同時多発した災害が発生しました。
宇治市に大きな影響を与える活断層地震には、
(1)黄檗断層
(2)宇治川断層
(3)生駒断層
があると想定されています。
宇治市のハザードの詳細については、宇治市危機管理室HP(https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/41-1-1-0-0_1.html)をご参照ください。
メイクスでは、京都府の「災害からの安全な京都づくり条例」に基づき、契約時の重要事項説明時に「洪水」 「土砂災害」「地震・津波」「防災情報」などの災害危険情報等のご説明をしております。また、その場所の災害(過去の浸水等)も重要事項としてご説明する必要があります。
ご検討されている場所が今どのようなハザードマップに入っているのか、過去に災害があったのか等ご不明なことがございましたらお調べ致しますので、何なりとご相談下さい。
関連記事
- お知らせ 2018年6月17日 家を売りたいけど近所の人に知られたくない
- お知らせ 2018年5月17日 不動産の買取制度とは
- お知らせ 2018年5月17日 不動産の所有者を調べる方法は?
- お知らせ 2018年6月17日 収益物件の維持修繕費はどれくらい必要でしょうか
- お知らせ 2024年3月11日 健康経営優良法人
- お知らせ 2018年6月17日 こだわりの注文物件を建てるためにアドバイスがほしい