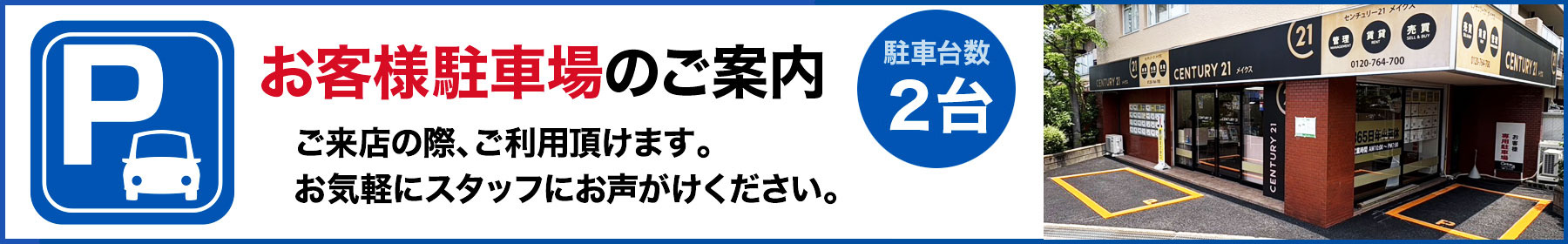2021年4月に民法が改正され、2023年4月に施行されました。
今回のブログでは、日々の生活の中で関係してきそうな「相隣関係」の改正について、ご紹介させていただけたらと思います。
※相隣関係とは、「隣り合う土地を所有する者同士が、自分が所有する土地を利用しやすいよう調整し合う関係」のことで民法上では隣り合う土地”のことを「隣地」と言います。
お隣に住む者同士誰もがトラブルなく平和な生活を送りたいですが、いざ問題が起こったときの判断の基準となるのが「民法」です。今回改正されたのは主に下記の3点です。
①隣地使用権の見直し
隣地使用権とは、一定の場合(たとえば自己の土地の外壁工事のため、一時的に隣地に入る、建物を修繕するのに必要な立ち入りなど)に、隣地使用を請求できる権利をいいます。
改正前の民法では、隣地使用権が認められるのは、「境界又はその付近において障壁又は建物を建造し又は修繕するため必要な範囲」と定められ、実際どのように行使するのかの方法についての規定はありませんでした。
改正で隣地使用権の範囲が拡大され、以下の場合に隣地を使用できるようになりました
第209条
土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
・境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
・境界標の調査又は境界に関する測量
・第233条第3項の規定による枝の切取り
2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
4 第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
②ライフライン設備の設置・利用について
自分の土地の電気、ガス、水道などのライフライン設備の設置、維持等のために他人の土地や設備などを利用しなければならないこともあります。
しかし、旧民法では、排水のための低地の通水(旧民法220条)等の規定しかありませんでしたが以下の条文が加わりました。
第213条の2
土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第1項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」 という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2 第1項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。
3 第1項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第209条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定を準用する。
4 第1項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第209条第4項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、1年ごとにその償金を支払うことができる。
5 第1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
6 第1項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
③越境した枝を自ら切除できる権利
旧民法では、隣地の枝が越境してきた場合にも自ら切除することができず、越境した竹木の所有者に切除させる必要がありました。しかし隣地所有者が切除に応じてくれない場合や隣地が所有者不明土地の場合は状況が改善されない場合があるなどの問題点がありました。
そこで、今回の改正では、越境された土地の所有者は、越境した枝を自ら切除することができるようになりました。
第233条
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
・竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
・ 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
・ 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
近年、所有者不明土地が増加し続けています。土地の所有者が不明であるときには、土地の利用や管理に支障が生じ、衛生や防犯に関して弊害が生じます。今般の民法改正は、社会問題に対する対策につながることが期待されます。
その他詳細はこちらにてご確認ください。
https://www.moj.go.jp/content/001360820.pdf
関連記事
- お知らせ 2025年4月7日 井川遊歩道〜桜〜
- お知らせ 2018年5月17日 不動産賃貸の管理会社選択の留意点
- お知らせ 2018年5月17日 駐輪場に入居者以外のものがあるのですが
- お知らせ 2018年6月17日 管理会社にどこまでの業務を任せるか?
- お知らせ 2018年6月17日 賃貸でエアコン交換の費用は貸主負担?借主負担?
- お知らせ 2019年9月23日 消費税10%の増税に伴う社会経済への影響について